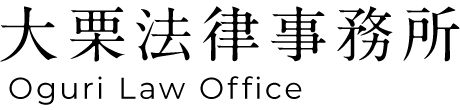従業員の解雇をお考えの経営者様へ
社員の解雇は、法律や手続きを誤ると大きなトラブルに発展する可能性があります。この記事では、企業側弁護士の視点から、解雇の種類や要件、退職勧奨との違い、問題社員への具体的な対応手順などを解説します。能力不足、勤務態度不良、企業秩序を乱す社員など、様々なケースに対応するための実践的なアドバイスをさせて頂き、違法行為によるリスクを回避するためのポイントを説明致します。また、企業側弁護士に相談するメリットやよくある質問への回答を記載しました。
-
解雇とは
解雇とは、会社が労働者との労働契約を一方的に終了させることを指します。労働者にとっては生活の基盤を失う可能性もある重大な出来事であるため、法律によって厳しく規制されています。安易な解雇は許されず、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。これらの要件を満たさない解雇は無効とされ、会社は労働者の雇用を継続する義務を負います。また、解雇には様々な種類があり、それぞれに異なる要件や手続きがあります。そのため、解雇に関するトラブルを避けるためには、解雇要件に関する基本的な知識を正しく理解することが不可欠です。
解雇の種類
解雇には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
|
解雇の種類 |
説明 |
|
普通解雇 |
労働者の能力不足、勤務態度不良など、労働者側の問題を理由とする解雇です。 |
|
懲戒解雇 |
横領、背任、服務規律違反など、労働者の重大な非違行為を理由とする解雇です。 |
|
整理解雇 |
会社の経営不振など、会社側の事情による人員整理を目的とする解雇です。 |
普通解雇
普通解雇は、労働者の能力不足や勤務態度不良など、労働者側に責任がある場合に行われる解雇です。能力不足とは、仕事に必要な能力が著しく欠けている、あるいは努力しても能力が向上しない状態を指します。勤務態度不良とは、無断欠勤、遅刻の常習、上司の指示に従わないなど、会社の規律を乱す行為を指します。普通解雇を行うためには、客観的に合理的な理由と社会通念上相当であることが必要です。また、解雇前に改善の機会を与えることも重要です。例えば、能力不足の社員には研修を受けさせる、勤務態度不良の社員には指導や注意を行うなど、解雇を回避するための努力が必要です。これらの努力にもかかわらず改善が見られない場合に初めて、普通解雇が認められます。
懲戒解雇
懲戒解雇は、労働者が横領や背任、暴力行為、セクハラなど、重大な非違行為を行った場合に行われる解雇です。懲戒解雇は、労働者にとって最も重い処分であり、会社の秩序を維持するために必要な最終手段とされています。懲戒解雇を行うためには、就業規則に懲戒事由として明記されていること、事実関係の調査を十分に行うこと、労働者から弁明の機会を与えることなどが求められます。また、非違行為の程度と会社の損害の大きさなどを考慮し、処分が相当であることも重要です。軽微な違反行為に対して懲戒解雇を行うことは、社会通念上相当とは認められません。
整理解雇
整理解雇は、会社の経営不振や事業縮小など、会社側の事情により人員整理が必要になった場合に行われる解雇です。整理解雇を行うためには、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続きの妥当性の4つの要件を満たす必要があります。人員削減の必要性とは、経営状況の悪化などにより、人員削減が不可避であることを示すものです。解雇回避努力とは、配置転換や希望退職の募集など、解雇以外の方法で人員削減を試みたことを示すものです。人選の合理性とは、年齢や勤続年数、能力などを考慮し、客観的かつ公平な基準で解雇対象者を選定したことを示すものです。手続きの妥当性とは、労働組合や労働者代表との協議を十分に行ったことを示すものです。これらの要件を満たさない整理解雇は無効とされ、会社は労働者の雇用を継続する義務を負います。
解雇の要件
解雇を有効にするためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
客観的に合理的な理由
解雇には、客観的に見て合理的な理由が必要です。労働者の能力不足、勤務態度不良、会社の経営不振など、解雇を正当化する理由が客観的に存在しなければなりません。単なる感情や個人的な好き嫌いによる解雇は認められません。解雇の理由が客観的で合理的であるかどうかは、最終的には裁判所によって判断されことになりますが、裁判所は会社の規模や業種、労働者の職種や地位、会社の経営状況などを総合的に考慮して判断します。
社会通念上相当であること
解雇は、社会通念上相当でなければなりません。たとえ客観的に合理的な理由があったとしても、解雇の程度が重すぎたり、手続きが不適切であったりする場合には、解雇は無効とされます。また、解雇前に労働者から弁明の機会を与えなかった場合も、社会通念上相当とは認められない可能性があります。解雇が社会通念上相当であるかどうかも、最終的には裁判所によって判断されることになりますが、裁判所は、会社の就業規則の内容、労働者のこれまでの勤務状況、解雇に至るまでの経緯などを総合的に考慮して判断します。
-
退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社が従業員に対して自主的に退職することを促す行為です。解雇とは異なり、従業員には退職に応じる義務はありません。
退職勧奨と解雇の違い
退職勧奨と解雇の最も大きな違いは、従業員の意思に基づいて退職するかどうかが決まる点です。解雇は会社の一方的な意思表示ですが、退職勧奨はあくまで従業員が退職するかどうかを選択できます。また、退職勧奨は合意に基づく退職であるため、通常は退職金が支払われますが、解雇の場合は、解雇の種類によっては退職金が支払われない場合があります。
|
項目 |
退職勧奨 |
解雇 |
|
従業員の意思 |
必要 |
不要 |
|
退職金 |
通常支払われる |
場合による |
|
法的根拠 |
なし(合意による) |
労働契約法等 |
退職勧奨の注意点
退職勧奨を行う際には、違法な退職勧奨とならないよう、十分な注意が必要です。違法な退職勧奨を行った場合、会社は損害賠償責任を負う可能性があります。
違法な退職勧奨とは
退職勧奨が違法となるケースには、以下のようなものがあります。
- 脅迫的な言動:退職に応じなければ不利益な扱いをするなどと脅迫する行為
- 退職強要:退職届の提出を強要する行為
- 不当な動機:人種、信条、性別、社会的身分、門地などを理由とした退職勧奨
-
問題社員への対応
問題社員への対応は、企業にとって頭を悩ませる問題です。適切な対応を怠ると、企業の業績悪化や職場環境の悪化につながる可能性があります。そのため、問題社員の種類を理解し、それぞれのケースに合わせた対応策を講じる必要があります。早期発見・早期対応を心がけ、状況が悪化する前に適切な措置を講じることが重要です。
問題社員の種類と対応事例
問題社員には様々な種類がありますが、大きく分けて以下の3つのタイプに分類できます。
能力不足の社員
能力不足の社員は、業務を適切にこなすことができず、周囲に負担をかけてしまう可能性があります。必要なスキルを習得するための研修や教育機会を提供し、それでも改善が見られない場合は、配置転換などを検討する必要があります。能力不足と判断する前に、業務内容や役割が社員の能力に合致しているかを確認することも重要です。例えば、営業成績が振るわない場合、営業以外の業務に適性がある可能性もあります。
具体的な対応事例としては、営業成績が低い社員に対して、営業研修への参加を促したり、営業以外の部署への異動を提案したりすることが挙げられます。また、目標設定を明確化し、定期的な面談を通じて進捗状況を確認することも有効です。
勤務態度不良の社員
勤務態度不良の社員は、遅刻や欠勤を繰り返したり、職場でのルールを守らなかったりするなど、企業秩序を乱す可能性があります。就業規則に基づいた厳正な対応が必要です。始末書の提出や懲戒処分などを検討する必要がある場合もあります。
具体的な対応事例としては、度重なる遅刻に対して、口頭注意や始末書の提出を求めることが挙げられます。また、無断欠勤が続く場合は、懲戒解雇も視野に入れる必要があります。
企業秩序を乱す社員
セクハラやパワハラ、情報漏洩など、企業秩序を乱す行為は、企業の信用を大きく損なう可能性があります。厳正な処分を行うとともに、再発防止策を講じる必要があります。また、被害者への適切なケアも必要です。社内調査を実施し、事実関係を明確にすることが重要です。
具体的な対応事例としては、セクハラ行為を行った社員に対して、懲戒などの処分を行うことが挙げられます。また、情報漏洩が発生した場合、原因究明を行い、再発防止策を策定する必要があります。
問題社員への対応手順
問題社員への対応は、以下の手順で行うことが効果的です。
|
手順 |
内容 |
注意点 |
|
事実確認と記録 |
問題行動の内容、発生日時、関係者などを詳細に記録する。 |
客観的な証拠を収集しておくことで、その後解雇した場合、解雇の要件を満たすかの判断にあたり、重要な証拠になり得ます。 |
|
指導・教育の実施 |
問題社員に対して、改善すべき点を明確に伝え、指導・教育を行う。 |
指導・教育の内容は、問題行動の内容や社員の状況に合わせて適切に設定する必要があります。また、実施した指導・教育内容を保存しておくことで、その後解雇した場合、指導・教育をしたにもかかわらず改善がみられなかったなどの意味で解雇の要件を満たすかの判断にあたり、重要な証拠になり得ます。 |
|
改善が見られない場合の対応 |
指導・教育を行っても改善が見られない場合は、配置転換や懲戒処分などを検討する。 |
改善が見られなかったことから直ちに解雇(懲戒解雇)をしてしまうと解雇要件をみなさない可能性が高いです。まずは、複数回にわたり指導・教育を行い、それでも改善が見られない場合には配置転換や戒告等の懲戒処分を検討し、最終的な手段として解雇(懲戒解雇)を検討することになります。 |
問題社員への対応は、企業にとって非常にデリケートな問題です。法的なリスクを回避するためにも、弁護士などの専門家に相談しながら進めることが重要です。適切な対応を行うことで、企業の健全な発展を守ることができます。
-
弁護士に相談するメリット
問題社員への対応は、企業にとって大きな負担となるだけでなく、法的なリスクも伴います。適切な対応を怠ると、大きな損害を被る可能性があります。特に、解雇の場面では、仮に解雇が無効と判断された場合、当該従業員との雇用契約が継続するだけではなく、解雇時から解雇無効と判断されるまでの間の賃金(いわゆるバックペイ)の支払義務を負う可能性があり、企業側としては負担が大きいものといえ、このような負担を回避するために、解雇に踏み切る前に弁護士に相談するメリットはあるものといえます。
専門家の視点で法的なリスクを回避
労働法の分野は複雑で、たびたび改正が行われています。そのため、最新の法令や判例を理解していないと、意図せず違法行為を行ってしまう可能性があります。そのため、当事務所では、労働法の専門家として、最新の法令や判例に基づいたアドバイスを提供致します。例えば、解雇や退職勧奨を行う際の適切な手順や、問題社員への対応における注意点などをアドバイスすることで、企業がトラブルに巻き込まれることを防ぎます。
また、就業規則の作成や見直しについてもサポートします。法的に有効な就業規則を整備することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
問題社員への対応方針策定のサポート
問題社員への対応は、状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。当事務所では、企業に寄り添いながら、個々のケースに応じて最適な対応方針を策定するサポートを行います。例えば、能力不足の社員に対しては、配置転換や研修などの適切な対応を提案します。また、ハラスメント行為を行う社員に対しては、懲戒処分や解雇などの厳しい措置も検討します。状況に応じて、内容証明郵便の送付や、労働審判、訴訟などの対応もサポートします。
-
解雇と退職勧奨に関するよくある質問
従業員の解雇や退職勧奨は、企業にとってデリケートな問題です。労働法に則った適切な手続きを踏まなければ、後々トラブルに発展する可能性があります。ここでは、解雇と退職勧奨に関するよくある質問をまとめました。
解雇予告は必ず必要ですか?
原則として、解雇する30日前までに解雇予告をする必要があります。これは労働基準法第20条で定められています。ただし、一定の例外として、即時解雇が認められるケースもあります。たとえば、従業員が重大な背信行為や犯罪行為を行った場合などです。また、天災禍変や事業の廃止など、やむを得ない事由がある場合も、解雇予告の期間を短縮または免除できる場合があります。
退職勧奨に応じない場合、解雇できますか?
退職勧奨に応じない従業員を、ただその理由だけで解雇することはできません。退職勧奨はあくまでも任意の退職を促すものであり、従業員には応じる義務はありません。退職勧奨に応じないことを理由に解雇することは、解雇の要件を満たさない可能性が高いです。解雇するためには、客観的に合理的な理由と社会通念上相当であることが必要です。
退職金は支払わなければなりですか?
退職金制度を設けている企業の場合、原則として退職する従業員に退職金を支払う義務があります。ただし、懲戒解雇の場合など、就業規則で退職金の支給を制限する規定がある場合は、支払われないこともあります。
解雇予告手当とは何ですか?
解雇予告手当とは、解雇予告がなされなかった場合、または解雇予告期間が30日に満たない場合に、使用者から労働者に支払われる手当です。これは、突然の解雇によって労働者が経済的に困窮することを防ぐための制度です。解雇予告手当の額は、解雇予告期間中に支払われるはずだった賃金と同額です。
問題社員への対応を弁護士に相談するメリットは?
問題社員への対応を弁護士に相談することで、法的に適切な対応を取りながら、リスクを最小限に抑えることができます。当事務所では、問題社員との面談に同席したり、内容証明郵便等文書の作成にあたっては、企業側の主張を効果的に伝えることを心がけています。また、訴訟に発展した場合にも、訴訟代理人として、企業側の明確かつ効率的に伝え、法的リスクを可能な限り軽減することを心がけております。
-
まとめ
従業員の解雇や退職勧奨は、企業にとって大きなリスクを伴う難しい問題です。
労働基準法などの法律を遵守せずに行うと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
特に、問題社員への対応は慎重に進める必要があります。
能力不足や勤務態度不良、企業秩序を乱す行為など、問題社員の種類に応じて適切な対応手順を踏むことが重要です。まずは事実確認と記録を行い、指導・教育を実施します。それでも改善が見られない場合は、解雇や退職勧奨を検討することになりますが、その際には客観的に合理的な理由と社会通念上相当であることが求められます。
違法な解雇や退職勧奨は、企業の信用を失墜させるだけでなく、多額の損害賠償請求につながる可能性もあるため、十分な注意が必要です。企業側の法律問題に精通した弁護士に相談することで、法的なリスクを回避し、適切な対応方針を策定することができます。
当事務所では問題社員への対応手順や法的根拠、紛争発生時の対応など、専門的な知識と経験に基づいたアドバイスを提供できるよう心掛けております。また、退職勧奨の手続きや内容の適法性、解雇の有効性などを判断し、トラブルを未然に防ぐ役割も担います。
関連ページ


労使紛争とは?紛争が発生した場合の会社側の対応や弁護士の役割を解説!!

解雇・退職勧奨とは?従業員を辞めさせる際に注意すべきポイントや具体的な進め方について弁護士が解説!
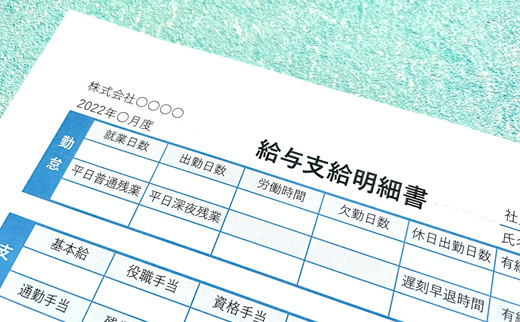
残業代請求をされた際の対処法とは?残業代請求対応について弁護士が解説!

団体交渉・労働組合対応とは?団体交渉の基礎知識と実践的な対応戦略について会社側弁護士が解説!

社内におけるハラスメント対処法とは?ハラスメントの類型とその対応を弁護士が解説!

メンタルに不調をきたした社員をどうすべきか?メンタルヘルス対応について弁護士が解説

労災対応とは?社内における労働災害の種類と請求を受けた際の対処法について弁護士が解説!
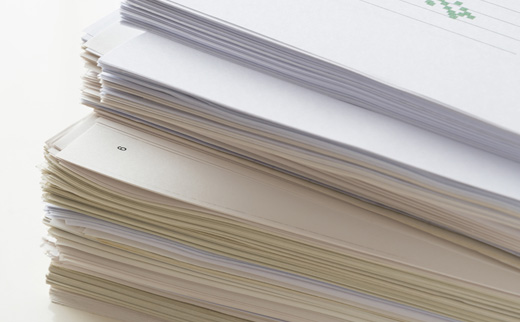
契約書のリーガルチェックの重要性とは?社内規定・書面整備が重要な理由について弁護士が解説!

労働基準監督署に通報されたら?労基署対応とその流れを弁護士が解説

公益通報窓口

社内研修