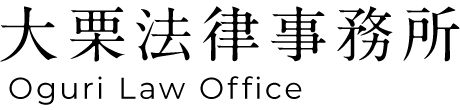解雇した従業員より依頼を受けた弁護士から解雇が無効である内容証明が届いたことから,弁護士に依頼し,従業員の代理人弁護士と和解交渉を重ねた結果,月額賃金約3か月分である約90万円を支払うことで解決できた事例
1.労使紛争対応事例の紹介
製造業を営むY社は,従業員や取引先との間でトラブルを発生させることが多い従業員の処遇に悩み当事務所に相談をしました。当事務所がY社からヒヤリングを行った結果,Y社は当該従業員の退職を臨んでいたことから,まずは退職勧奨を行いましたが,当該従業員はこれに応じませんでした。そこで,当事務所のサポートのもと,当該従業員に対して業務改善命令書を作成して交付したり,配置転換などを行いましたが,当該従業員によるトラブルは解消されず,やむを得ず,Y社は,能力不足を理由に,当該従業員を解雇しました。
その数日後,当該従業員から依頼を受けた弁護士から解雇が無効であるとする内容証明が届き,Y社の代理人弁護士と受任しました。
当事務所は,当該従業員の代理人弁護士と交渉を重ね,これまで当該従業員に交付した業務改善命令書や解雇に至った理由,当該従業員が作成した反省文の内容などを説明し,結果として,当該従業員の代理人弁護士との間で,月額賃金約3か月分である約90万円を支払うことで和解しました。
解雇の有効性についての立証責任は会社側にあり,特に能力不足の事案では立証のハードルは高いといえいます。明らかな能力不足の事案でも,会社側が解雇に至るまでの手順を間違えてしまうと,バックペイの問題など大きなリスクを負担します。仮に,解雇が有効であったとしても,その争いが訴訟まで発展してしまうと解決まで1年以上かかるケースが多くみられます。本件は,過去の裁判例と比較し,解雇の有効性が微妙であったことを踏まえ,Y社と協議した結果,上記のとおり解決することとなりました。
2.労働紛争の解決手段
解雇した労働者が解雇の有効性を争う場合,労働者が弁護士に依頼をして会社に内容証明を送付したり,行政機関にあっせん手続を求めたり,会社に対して任意での交渉を求めることがあります。この任意交渉で,解決に至らない場合,労働者は主に以下の方法を取ることが考えられます。
- 労働審判
- 仮処分
- 民事訴訟
⑴ 労働審判
労働審判とは,会社と労働者との間で起きた労使間の紛争について,迅速に解決するための手続です。原則として3回以内の期日されており,労使間で和解が成立しなければ,「労働審判」が下されます。「労働審判」に不服があれば,民事訴訟に移行します。
原則3回までですが,実務上,第1回期日において,双方の主張を整理して事実関係を確認し,場合によっては審判官の心証が開示され,和解の話が進むことが多いです。仮に,第1回期日において,誤った事実関係や法的主張をしてしまった場合,労働審判においては取り返しのつかないことになりかねません。
したがって,労働審判においては,第1回期日までが勝負といえ,第1回期日前までに,事実関係を調査し,必要な法的主張を整理して,書面にまとめて証拠とともに提出する必要があり,タイトなスケジュールで準備しなければなりません。特に使用者側は,労働者側からの労働審判申立書が届いた際には第1回期日が指定されており,そこから短時間で第1回期日前までに準備しなければならず,事実関係の調査や必要な法的主張を会社内で整理することは難しく,法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいといえます。弁護士に依頼することで,迅速に事実関係を整理し,本件事案に必要な法的主張をわかりやすく主張することで,第1回期日から審判官に誤解なく,適切な事案の解決につながるものといえます。
⑵ 仮処分
労働事件の仮処分とは,民事訴訟手続の結論を待っていては,生活が困窮するなど労働者に著しい損害または急迫の危険が生じる場合,裁判所が暫定的に必要な措置を命じる民事保全手続の1つです。
労働者が被保全権利の存在(解雇事案であれば雇用契約条の権利を有する地位の存在)と保全の必要性(生活が困窮しているなどの事情)を主張して,裁判所に,暫定的に従業員としての賃金を求めることになります。
民事訴訟は平均1年以上の時間がかかり,労働事件においては2年以上の時間がかかることも珍しくありません。その間,解雇事案の場合においては,給与が得られなくなり,生活が困窮する可能性があります。
そのための手続が労働事件の仮処分であり,労働者にとっては,暫定的ではありますが,民事訴訟手続解決する前に救済を受けられるというものです。
⑶ 民事訴訟
上記のとおり,労働事件の民事訴訟では2年以上の時間がかかることも珍しくなく,解雇事案では,労働者は生活が困窮してしまうことから,民事訴訟を提起する前に仮処分の申し立てをすることがあります。
もっとも,仮処分手続では,文書提出命令などを申し立てることができないことなどから,重要な証拠が労働者側になく,会社側から任意提出が期待できない場合には,仮処分を申し立てることなく民事訴訟を提起する場合も見受けられます。
また,解雇事案において解雇の有効性が否定された場合,会社と従業員との間の労働契約は継続していたことになり,会社は従業員からの労働提供を拒否していたことになり,反対に,従業員から会社に対する賃金請求は残ります。すなわち,会社は,従業員から労働提供を受けていなかったにも関わらず賃金を負担しなければならず,民事訴訟が長引けば長引くほどその未払賃金額は増加します。これがバックペイの問題で,会社としてはこの問題を抱えながら,民事訴訟を継続することになりますので,労働事件,特に解雇案件については,解雇の段階,解雇後任意交渉の段階,労働審判や仮処分の段階など,民事訴訟に移行する前に慎重な判断が必要になり,民事訴訟においてどのような結果になるかを正確に分析するため,労働事件に精通した弁護士によるアドバイスは必要といえます。
3.弁護士からのアドバイス
当事務所は,当事務所と顧問契約を締結させていただいている企業様に,特に解雇事案においては,必ず事前に相談するようにアドバイスをしております。
解雇が難しい案件については退職勧奨の方法やその注意点を説明させていただき,解雇の有効性が認められるような案件についても,過去の裁判例に基づき,解雇に至る過程で手続上問題が生じないようにアドバイスをしております。
関連ページ


労使紛争とは?紛争が発生した場合の会社側の対応や弁護士の役割を解説!!

解雇・退職勧奨とは?従業員を辞めさせる際に注意すべきポイントや具体的な進め方について弁護士が解説!
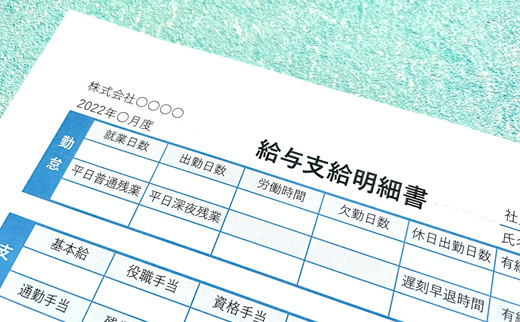
残業代請求をされた際の対処法とは?残業代請求対応について弁護士が解説!

団体交渉・労働組合対応とは?団体交渉の基礎知識と実践的な対応戦略について会社側弁護士が解説!

社内におけるハラスメント対処法とは?ハラスメントの類型とその対応を弁護士が解説!

メンタルに不調をきたした社員をどうすべきか?メンタルヘルス対応について弁護士が解説

労災対応とは?社内における労働災害の種類と請求を受けた際の対処法について弁護士が解説!
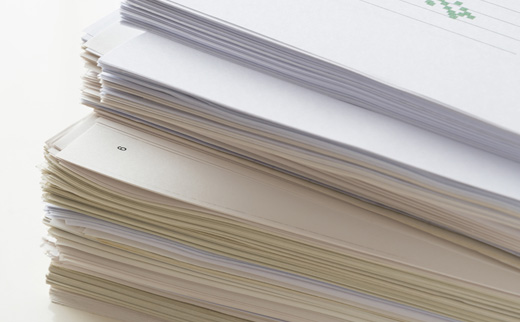
契約書のリーガルチェックの重要性とは?社内規定・書面整備が重要な理由について弁護士が解説!

労働基準監督署に通報されたら?労基署対応とその流れを弁護士が解説

公益通報窓口

社内研修